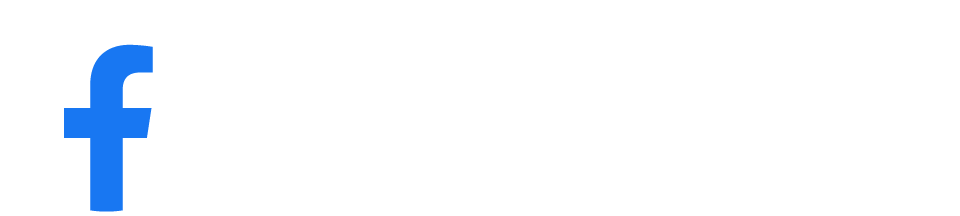トモデココグループでは、すでに児童発達支援事業所で「アロマと光の効果」を活用した支援ルームづくりをしています。
また、秋にオープンする「トモデココアトリエ」でも子どもたちの安心と成長を支える新たなアプローチとして、光や音、香り、触覚など、五感にやさしく働きかける「スヌーズレンの理論の導入」を計画しています。
スヌーズレンの効果的活用法を学ぶ
「スヌーズレン」は、心地よい空間の中で一人ひとりが自分らしく過ごせる支援方法として、近年大きな注目を集めていますが、その本質理解はまだまだ広がっていません。
そこでトモデココグループでは、より適切で効果的な活用に向けて、スヌーズレンの第一人者である大崎博史氏をお招きし社内研修を開催しました。
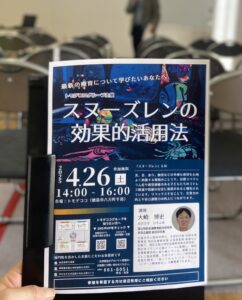
本記事では、国際スヌーズレン協会理事、日本スヌーズレン研究会副会長を務める大崎氏から教示を受けた「スヌーズレンの歴史や効果、国内外での導入事例」を交えながら、トモデココアトリエでの活用への思いをご紹介します。

「新しい療育方法を試してみたい」「もっと効果的な支援を受けさせたい」と考えている保護者の皆さま、ぜひ最後までご覧ください。
1. スヌーズレンとは? ~歴史と基本理念~
スヌーズレンは、1970年代、オランダの知的障がい者施設で誕生しました。
その語源は、オランダ語の「スヌッフレン(鼻でクンクンにおいをかぐ)」と「ドースレン(ウトウトする)」を組み合わせたものです。
「スヌーズレンは、多機能な概念をもつ。特別に設計された部屋の中で、光や音(音楽)、香りの使用は、人にリラックス効果と活性的な効果の両方が知られている。」(Martens, 2003・2005年、訳:姉崎 弘)
スヌーズレンの本質
スヌーズレンの本質は、「誰もが安心し、自由に自己を表現できる空間」を創り出すこと。療育や治療だけでなく、発達促進やリラクゼーション、余暇活動の支援としても幅広く用いられています。
発祥の地であるオランダにはThe centre De Hartenberg に「スヌーズレン・パビリオン」があり、デンマークには世界最大規模のLandsbyen Sølund があります。
そこには産道をイメージさせる赤く柔らかい光に包まれた入り口、ウォーターベッドが敷かれファイバーグローカーテンのあしらわれた白く明るい部屋、触覚に働きかける仕組みやボタンを押すと特定の香りが出てくる仕掛けが施された場所など、さまざまな空間があります。
日本でもスヌーズレンを導入する施設や団体がありますが、「暗い空間に、光を浮かび上がらせる」というブラックルームが先行し、「スヌーズレンの理念や本質」を届けるところに至っていないというのが現状です。

2. スヌーズレンの効果 ~心と身体に寄り添う支援~
スヌーズレンがもたらす主な効果には次のようなものがあります。
-
リラックス効果:心身の緊張をほぐし、不安感やストレスを軽減
-
感覚統合の促進:五感への穏やかな刺激によって、感覚の調整力を育む
-
情緒の安定:安心できる環境が、情緒の安定と自己表現を促進
-
人間関係の構築:対象者と介助者との間に信頼と共感を育む
「スヌーズレンとは、対象者のニーズに応じて、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚などを適度に刺激する、人工的な多重感覚環境を部屋や教室などに創出し、対象者と介助者(または指導者)と環境の三者間の相互作用により、対象者の主体性や相互の共感を重視して支援する活動である。」(姉崎 弘, 2013)
- これらはすべて、障がいのあるなしに関わらず、自分を解放したり、本来の力を発揮するために必要な要素でもあるのです。
あなたがリラックスするために必要なものはなんですか?
もしも、いまあなたがこんな条件に囲まれていたら、どうでしょう。
- ストレスなくリラックスした環境
- 自分にとって心地よい刺激がある空間
- 自分の興味関心のあることに夢中になれる時間
- 近くにいる人と信頼し合える人間関係
最高のコンディションで、いつも以上の力を発揮し、家事や仕事、スポーツや趣味を満喫することができるのではないでしょうか。
あなたのお子様にとっての幸せの条件とは?
ところが、発達障がいを持つ子どもたちは、「どうしてこれができないの」「もっと頑張って」と求められる場面がどうしても多くなります。
「また失敗してしまった」「なぜ自分はみんなのようにできないんだろう」と自分を責めることもあるかもしれません。

では、そんな子どもたちにとって「ストレスなく安心できる環境」はいったいどこにあるのでしょうか。
みなさまも、どうぞこの機会に、お子さまが安心できるために必要なものはなんだろう、と思い浮かべてみてくださいね。
スヌーズレンは「自ら主体的に活動する力を伸ばす」ためのもの
発達障がいのある子どもたちは、学校で、家で、外出先で、やりたことや好きな事に制限をかけられることが自然と多くなってしまうのが現実です。
そんなときに、大好きな毛布に包まれてベッドの上で寝転べたら・・・・
満足いくまでドスンドスンと飛び跳ねることができたら・・・。
ひと目を気にせず、大きな声でわーーーーと叫ぶことができたら・・・・・。
いますぐ、気のすむまで、どこまでも走っていけたら!

「リラックスできる環境でこそ、人は自ら主体的に活動することができる」と大崎氏は話します。
ストレスなく、安心して、誰になんの制限もかけられず、自分のやりたいように自由にできる時間や空間があってはじめて、子どもたちは自己理解が進み、自己肯定感を育み、力を発揮することができるのです。

3. 世界と日本に広がるスヌーズレンの導入事例
スヌーズレンは、オランダをはじめ、イギリス、ドイツ、アメリカなど多くの国で知的障がい児・者、高齢者、発達障がい児支援の現場に導入されています。
海外の事例
発祥の地であるオランダのスヌーズレン・パビリオンは、近隣の地域に開放され、特に重度の知的障がいのある人達が活動の一環として自由に利用できます。
アディダスの本社には「スヌーズレンルーム」があり、リラックスすることで本来の力を発揮できる仕組みもあります。
デンマークの小学校では、「スヌーズレン」の理念を活用し、教室の一角に「気持ちを落ち着かせる空間」を設置。「つらいなぁ」と感じたときに子どもたちが自由に、授業中でも自分に移動し、授業の様子を見ながら、横になったり、好きなものに囲まれたりして心を整えることができるスペースを確保しています。
ほかにも医療機関、福祉施設で、スヌーズレンルームが子どもたちの情緒安定やストレス緩和に役立っていると報告されています。

日本国内の事例
日本でも、特別支援学校や児童発達支援センター、放課後等デイサービスなどで徐々に導入が進んでいます。
埼玉県立騎西特別支援学校では、施設内のスヌーズレンルームのリニューアルや機器の購入のためクラウドファンディングを実施していました。
また期間限定で企業と特別支援学校のコラボレーションによるスヌーズレン検証が行われたりしています。
国立特別支援教育総合研究所(参考:スヌーズレンの紹介)では、日本におけるスヌーズレンの普及・研究が進められ、導入した施設からは、「子どもたちが落ち着いて自己表現できるようになった」「集団生活への適応がスムーズになった」といった報告が寄せられているそうです。
4. スヌーズレンの理念 ~心地よい環境づくり~
国際スヌーズレン協会理事、日本スヌーズレン研究会副会長を務める大崎博史氏は、研修のなかで「『ザ・スヌーズレン』というものはない。そこにあるのは『スヌーズレン』という理念だけと言えるかもしれません」と繰り返し話されていました。
探索活動は好奇心の芽になる
スヌーズレンの基本理念は「特に、障がいのある人が、視覚、聴覚、触覚、嗅覚等の感覚を活用し、心地よい環境の中で自由に探索活動を行える環境づくりを進めること」です。
モノに触ったり、なめてみたり、落としてみたり、それらはすべて「自由な探索活動」と言えます。
発達障がいのあるお子様のこうした活動・行動を目にすると、つい周囲は「危ない!」「ダメよ」と制限をかけてしまいがちです。

しかし制限を繰り返していると「学び」の要素である「知的好奇心」の芽を摘んでしまうことになります。
スヌーズレンを通して、幸福感を感じ、自発的行動を増やす
「自由な探索活動」を増やしてあげたいという気持ちはあるけれど、普段はなかなかできなかったり、保護者の方にとってご負担になることもあるかもしれません。
だからこそトモデココグループでは、「スヌーズレンの理念」を適切に取り入れ、「心地よい環境づくり」「関わり方の工夫」「一人一人の幸福感の追求」に注力したいと考えています。
研修のなかで大崎博史氏は「『スヌーズレン』とは理念のことであり、『これがスヌーズレンです』という手法を明示しているものではないのです」と繰り返しお話されていました。
私たち職員も最初は「光や匂いをどう活用するか」を考えるのに必死でしたが、今回の研修を受けたことで、「スヌーズレンの理念を全員が正しく理解し、共有し、支援に活かすことこそ大切なのだ」ということにハッとさせられたのでした。

また研修を通して、スヌーズレンの導入には重要なのは「無理に参加させるのではなく、その子自身の自発性を尊重すること」だと学びました。
そしてなにより、スヌーズレンを導入するということは、子どもたちへの関わり方のなかで、「この子の幸福感とは何だろうか?」と一人一人の生き方に目を向けた支援を目指すということにほかならない、ということにも気付けたのです。
5. トモデココアトリエでのスヌーズレン活用
トモデココアトリエでは、秋のオープンに向けて、スヌーズレン空間の整備を進めています。
建物の建築はこれからですが、コンセプトは「子どもたちが自分らしくいられること」です。
静かな光、やわらかい音楽、心地よい香りなど、五感に働きかける特別な環境を整え、子どもたちが安心して自分のペースで過ごしながら、自発的に行動できる取り組みを柱にしていきます。
また「保護者会Tomoに育つ会」の開催や保育所等訪問支援を通して、保護者の皆さまにとっても、「安心して子どもを預けられる場所」となるよう、スタッフ一同取り組んでまいります。


6. 新しい療育を一緒に体験しませんか?
「スヌーズレン」という新しい療育方法は、子どもたちにとっても、保護者の皆さまにとっても、新たな可能性を開く支援手法です。
トモデココアトリエでは、子どもたちの「できた!」「楽しい!」という小さな成功体験を積み重ね、自己肯定感を育む支援を目指しています。
「もっと子どもが自分らしく過ごせる場所を探している」
「最新の療育手法に触れさせてあげたい」
そんな想いをお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。
トモデココアトリエについて
トモデココアトリエの利用について相談する▶ 電話 088-661-6051(放課後等デイサービストモデココ/斎藤)
トモデココアトリエの「見学・体験※」を相談する▶ 電話 088-661-6051(放課後等デイサービストモデココ/斎藤)
※アトリエの施設見学は9月ごろから可能です。それまでは、トモデココグループでの「見学・体験利用」をご案内しています。